今回は、法人設立を考えている皆さんに知っておいてほしい8つのことをご紹介したいと思います。
この8つの内容は、一部をご存知の方もいるかもしれませんが、すべてを意識している方はなかなかいないと思います。
どれもスタートアップを支援してきた私が実務を通して感じていることで、書籍などにはのっていない現実のことです。
記事は少しボリュームがあるため青字のみ拾い読みをしていただいてもよろしいかと思います。
1 会社形態について
近年では、会社設立というと株式会社か合同会社の設立であることがほとんどです。
では、設立形態として一体どちらの形態で設立すべきなのか?
これについて私見を述べていきたいと思います。
なぜか勧められる合同会社
インターネットで検索してみると株式会社と合同会社の比較が掲載されています。
法律的には様々な違いがあり、上手に使い分ける必要があると思いますが、実務上、選択基準となってしまっているのは、10万円ほど安くなる設立費用です。
司法書士さんや行政書士さんが設立費用が安くなることを理由に安易に合同会社を勧めているケースが散見しています。
私が株式会社を勧める理由
私は法人形態の相談をされた場合、株式会社を勧めています。
合同会社も立派な法人です。
しかし、歴史も浅く、知名度は株式会社の足元にも及びません。
合同会社のほうが安く設立できることは確かです。
しかし、10万円程度安くなるだけです。
税負担も考慮すれば持ち出しは6万5千円程度です。
これから事業を大きくして行こうと考える場合、最も大事なのは信用力です。
その信用力を6万5千円程度で判断される場合もあることを十分考慮すべきです。
2 本店所在地について

本店所在地は最初は自宅であったり、親の自宅としている方が多くいらっしゃいます。
ただ、本店を安易に決めてしまい、後悔するケースもあります。
実務でよくある失敗は補助金や融資制度です。
財源の問題で一般的には都市部のほうが制度は充実しています。
今回のコロナ禍に伴う都道府県や市区町村の独自の給付は大きく各地で異なっていることを見れば一目瞭然です。
このような違いはコロナ禍ではない平常時でも常に存在します。
本店所在地をどこにするかは商売をしていくうえで極めて重要な事項です。
そのため、慎重に決定すべき事項ですが、甲乙つけ難い場合には各候補地の中小企業に対する公的施策を比較検討してみることも一案です。
3 決算日

決算日を何月にするかも重要です。
戦略的に考えるには以下3つのことを総合勘案して決めましょう。
- 消費税の納税
- 融資を念頭に置く
- 売上が最もあがる月
① 消費税の納税義務
消費税の免税期間は可能な限り、長くとりたいところです。
そのため、予想される年間売上(個人事業をされていた方であればすぐに推測できると思います)や従業員の給与により初年度を丸々一年にするか、7か月後の決算にするかを検討します。
② 融資を念頭に置く
会社設立当初から潤沢に資金をもっている場合は気にしなくてもよいのですが、スタートアップの際は何かと資金が不足します。
政策金融公庫の新創業融資などは実績がない方が受ける融資のため、決算書の代わりに事業計画書の提出で良いですが、事業開始後に資金が不足すれば融資を受けるために決算書が必要になってきます。
しかもビジネスローンを受けるのでれば最低でも2年分(24か月)、出来れば3年分は欲しいところです。
そのような切り口で考えてみると第一期目の決算書に意味を持たせるためにも初年度は最低でも半年以上の月数はほしいところです。
③ 売上が一番上がる月は何月か?
企業にとって、資金繰りは非常に重要です。
融資を受けやすくするために決算内容をよくしておく必要があります。
そのためには黒字決算は必須です。
ただ、利益は上がらないと困りますが、上がりすぎても困ります。
これを念頭に考えた場合、売上が一番上がる月を期首にもってくることも一案です。
4 会社の目的

会社の目的は全部事項証明書に記載される重要な情報です。
後から追加も出来きますが、追加するためには手間とお金がかかります。
そのため、将来やりたいと思っている業種や、可能性があるものはとりあえず目的に記載しておこうと考える方が多いです。
(実際そのような案内をされている方も多いようです)
しかし、実は落とし穴があります。
その後の融資に大きく影響する場合があるのです。
融資を受ける際、ほとんどの場合、保証協会という機関に保証してもらい金融機関から融資を受けますが、一定の業種はこの保証外とされているのです。
このことを知らずに会社の目的に安易に対象外の業種を入れ込んでしまうと、このことが後々響いてくることがあるのです。
また、許認可が必要な業種の場合には、その許可が取れているかどうかも重要になってきます。
(参考)埼玉県信用保証協会HPより(ご利用になれる方の業種要件)
一般にいう商工業者のほとんどの方が利用できます。
ただし、農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等は原則として保証の対象となりません。
許認可証の確認が必要となる業種に記載された業種を営む方で許可等を要する場合、保証申込時に原則としてその許認可証の写しを当協会に提出する必要があります
5 資本金の額

設立準備を進めるにあたり、資本金をいくらにすべきか?といった問題は非常に多く頂く質問です。
この質問に対する答えとしては、5つの視点により検討してもらっています。
- 資本金1千万未満
- 信用力の問題
- 許認可による最低資本金額
- 運転資金
- 資金調達
① 資本金1千万円未満
法人設立をする際、資本金を1千万円以上とした場合、初年度から消費税の納税義務が発生します。そのため、一般的には資本金は1千万円未満とするケースが圧倒的に多いのが現状です。
② 信用力の問題
近年は最低資本金の考えがなくなり、1円からでも会社が作れるようになりました。
そのため、資本金は極力入れたくないという方がいます。
しかし、私は可能であれば300万円以上の金額を資本金としてもらうことにしています。
理由は明白です。
例えば、新しく取引をする会社の登記簿謄本を確認したときに資本金が1円であった場合、みなさんは取引をしますか?ちょっと考えてしまうのではないでしょうか?
300万円以上が望ましいと考えている理由は明確な根拠はありません。
ただ、現在も残る有限会社の最低資本金額だったからです。
昔から、会社のほうが信用力があるといわれてきましたが、それは最低でも300万円なければ会社が作れなかったからだと考えているからです。
③ 許認可の問題
資本金の問題でうっかり忘れがちなのが許認可の問題です。
例えば、設立当初から建設業の許可を取ろうとする場合には500万円が必要です。
法人成りしたあとに許認可を受ける必要がある場合には、自身が取得する許認可について最低資本金要件がないか事前にリサーチしておく必要があります。
④ 運転資金
既に個人事業をしていた方が法人成りする場合、当面の運転資金の予測はつくと思います。
しかし、事業開始とともに法人化する場合には、当初考えているよりも意外に運転資金は多く必要となります。
そのため、予測される当面の運転資金よりも多めの資本金として入れておく必要があります。
※運転資金が乏しいとお金の心配ばかりすることになり、重要な本業がおろそかになってしまいます。独立する前に当面の資金は確保することが理想です。
⑤ 資金調達
創業融資を受ける場合に最も重要となるのは自己資金です。
個人事業をしていた場合には実績があるため、融資時に実績をアピールができますが、新規に事業を始める場合には、前職での経験のほか、自己資金が重要な判定要素になります。
例えば、日本政策金融公庫の新創業融資における自己資金要件は10分の1以上が目安とされていますが実際の肌感覚としては3分の1以上が必要です。
これは日本政策金融公庫のHP上で明らかにされている「よくある質問Q4。自己資金はいくら必要ですか」でも明らかです。
制度融資を受ける際も同様です。少ない資本金だけで窓口となる金融機関にお断りされてしまっているケースもあります。
金融機関の担当者から断られた理由を聞いてみると「資本金の額(自己資金)が・・・」といったことが過去に何度もありました。
更に資本金をなるべく積んでほしい理由は資金調達をするために債務超過を避ける必要があるからです。
債務超過という言葉をどこかで聞いたことがある方も多いと思います。
債務超過とは簡単に言ってしまえば会社を始めたときのお金と経営して得た利益の合計がマイナス残になってしまうことです。
この債務超過に陥った会社に対して金融機関は慎重な態度を示します。
会社を起動に乗せるまでには時間がかかります。
そして軌道に乗せるためには資金調達は最重要課題です。
6 役員について

会社設立時には役員について下記のことを決める必要があります。
- 代表取締役(社長)を誰にするのか
- 誰に役員をやってもらうか
- 役員の任期は何年にすればよいか
① 誰を代表取締役にするか
実務上問題になるのは、本来はご主人が社長になるべきところを奥さんが社長になっているケースです。
理由を聞いてみると「まだ会社に勤めているから副業規定に引っかかるので取りあえずは奥さんを代表取締役に・・・」という場合が多いです。
しかし、これはあまりお勧めは出来ないと感じています。
本人は軽い気持ちで行った行為ですが、金融機関は以下のように考える傾向があります。
「実質の代表者であるご主人は、過去に金融事故を起こしているのではないか?信用情報をとって出てこなくても可能性がありそうだから今回は別の理由をつけて断ろう。」
「実質的な代表者は夫なのに副業禁止のため奥さんが社長とは本当に事業を継続していく気があるのか?途中で事業を廃業する可能性が高いのでは?」など。
金融機関は実質の経営者は誰であるのか必ず確認しますし、非常に重要視しています。
そして、実質経営者が代表取締役でない場合には融資に難色を示す場合がほとんどです。
メリットとデメリットをよく比較し、慎重に決めましょう。
② だれを役員に入れるか
実績がある人を引っ張りこむために名前だけでも役員になってもらおうと考える起業家も多いようです。
しかし、名前だけの役員が原因で融資を断られるケースも存在します。
その役員が過去に金融事故を起こしているような場合には要注意です。
③ 役員の任期は何年にすればよいのか?
平成18年の会社法改正により役員の任期は10年まで伸ばせるようになりました。
10年にするメリットは登記の手間や費用を抑えらえることです。
しかし、デメリットもあります。
例えば、第三者を役員に入れ任期を10年にすると当然ながらその方は原則10年間は役員です。
しかし、10年の間に経営状況やその方との関係性が変化していくのはごく自然のことです。
良い関係性が維持出来ているのであれば問題ないのですが、関係性が悪化し、関係を解消しようとしたときに任期期間中であれば解任理由に合理性が認められないときには損害賠償請求をされるリスクがあります。
手間と費用はかかってしまいますが、2年間の任期であれば、上記のリスクは最小限に抑えることが出来ます。
安易な人選により、損害賠償までは行かなかったものの一歩手前までこじれてしまったことは一度や二度ではありません。上記の①②と同様、役員の人選、任期ともよく検討する必要があります。
7 株主のこと
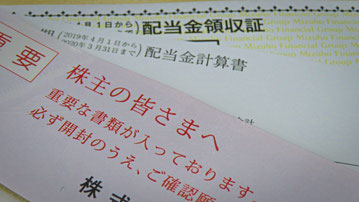
株主に誰がなってもらうかは非常に重要です。
役員の選任、役員報酬の決定、配当金の金額決定、会社の定款変更、合併や解散など会社の重要事項はすべて株主(株主総会)が決定します。
代表取締役がすべての株式を保有しているような場合には株主総会は形骸化しているケースがほとんどです。
しかし、株主が複数人いるような場合には注意が必要になってきます。
株主を普段から意識している中小企業は少ないですが、関係性が悪化した場合には会社が機能不全に陥る可能性があり、むやみに株主を増やすことは控えたほうがよいでしょう。
8 節税

法人化を検討する最も多い理由かと思います。
しかし、同時に私が最も反対する目的でもあります。
確かに税金だけを考えると得になるケースは多くあります。
しかし、社会保険・法人の維持費(税理士費用等)なども考えるとメリットが大きく出てくるケースは意外に少ないのが現状です。
消費税の納税義務が2年間外れるとしても、それは一時的に外れるだけであり、タイミングは売上が1千万円を超えたときでなくてもよいわけです。
もし、節税目的で法人成りするのであれば、税金だけではなく、社会保険や維持費用も含め、十分効果が望めるかどうかも検討し、法人を設立されることをお勧めします。
さいごに
最近はリーズナブルな料金で会社設立関係資料をダウンロードし、会社設立手続きを自分で行う方が多くなっています。
しかし、それに伴い会社設立の前に当然検討すべきことがされていない場合に多く遭遇します。
会社設立前に相談に来てくれていたら・・・・といったことも1度や2度ではありません。
会社設立は人生の重大イベントです。
スタートアップで躓かないためにも安易な設立は避け、しっかり理解したうえでスタートを切ってください。


